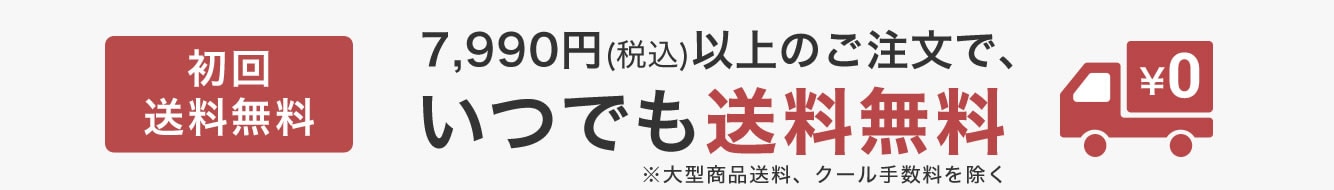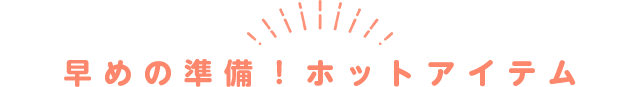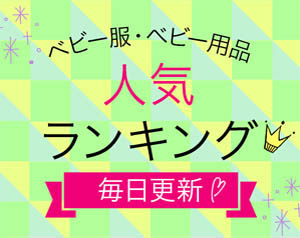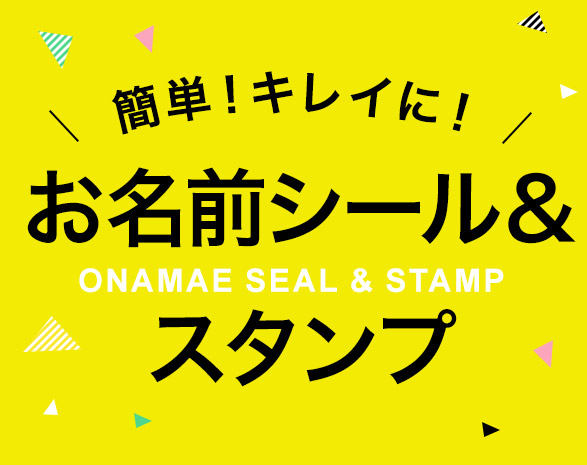ママフル365コラム 【保育園長のナルホド育児】○○すれば、苦手なものも食べられるように!?

子どもたちの成長を見守り続ける保育園の先生から、子どもの好き嫌いをなくすコツついて教えてもらいました。
教えてくれた人:えがおの森保育園・せんごく 堤園長先生
きちんと食事をとることの大切さ
バランスよくしっかり食べられることは、体力があって、病気にかかりにくい子どもに育つことにつながります。私の経験上、特に0歳~2歳のあいだは「ごはんをたくさん食べ、いっぱい遊び、よく眠る」。この3つがきちんとできていれば、大きくなっても風邪などをひきにくい子に育つと思います。
理想は何でも食べてくれること。でも現実はキビシイ!?
子どもによって苦手な食べものはさまざま。野菜がキライな子もいれば、魚が食べられない子もいます。からだのことを考えると、何でもバランスよく食べてほしいのが親心というもの。少しでも苦手を克服できるよう、料理を工夫しているママも多いと思います。
それでも食べてくれなくて困っているなら、保育園でも実践している「子どもたちの好き嫌いをなくすコツ」を試してみてください。
保育園でも実践中【好き嫌いをなくす4つのコツ】
「まずは一口だけ」を目指す
保育園では、給食で苦手な食べものが出た場合でも「必ず一口は食べる」というルールをつくっています。食べたいものだけたくさん食べるのではなく、また苦手なものを避けるでもなく。食べたいものは普通に、苦手なものは一口だけパクッと。
地道な方法ですが、このルールを毎日くり返すと、だんだん食べられるようになる子どもが本当に多いんです。
食べた直後に二口めを誘導してみる
子どもが一口食べた時に「どうだった? おいしかった? もう一回食べてみる?」と聞いてみることも有効。思わず「うん」って言ってしまう子……意外と多いです! ここでのポイントは、二口めも食べられたら、たくさん褒めてあげてください。自信がついて苦手なものも少しずつ食べられるようになり、そのうち食事自体をバランスよくとれるようになります。
空腹は最高の調味料!
お腹が空くまでいっぱい遊ばせた後に、苦手なものを食事の最初に食べさせてみてください。空腹だとキライなものがいつも以上に食べやすかったりします。
その時、保護者の方もぜひ子どもと同じものを、一緒に食べてあげてくださいね。
食べきることの達成感を教える
保育園では3歳児クラスから、自分で食べる量を考え、先生に申告するルールがあります。
食育では苦手なものを食べることだけでなく「自分で食べる量を決めて、最後まで食べきる」という感覚を身につけることも大切。お皿がピカピカになる喜びを知ることは、苦手な物を食べられることにつながります。
成長とともに食べ物の好みが変わり、苦手だったものをあっさり食べられるようになることもあります。好き嫌いをなくすのは、焦らず、子どものペースに合わせて進めていきましょう。
食事にまつわる「お悩みあるある」。こんな時どうする?
保育園では食欲旺盛らしいのに、家ではご褒美がないと食べてくれない……
「ごはんを食べたくない」という子どもに対して、ご褒美のジュースなどで釣ってなんとか食べさせるという話はよく聞きます。
もしかすると子どもは園で頑張っている分、おうちでママやパパに甘えているのかも。でも、子どもも知恵がつくので、ご褒美をくり返すと要求が増長してしまいます。
まずは親が「ここまでは良いけど、ここから先はダメ」とラインを決めること。そして一度決めたラインは崩さないことが重要です。子どもだけでなく、ママやパパも子どもと同じラインを共有してくださいね。
約束したラインをなし崩しにすると、子どもは「ダメって言ってたのに、いいんだ」と認識してしまい、どんどん「試し行動」が増えていきます。だから最初のラインを崩さないことがとっても大事なんです。
食べている途中、ジッと座ってられず動き回る
これはしつけのお話。食事中に動き回る子どもは、保育園でもたくさんいます。ママ・パパは、お子さんに座ってほしいのでしょうか? それとも食べてほしいのですか?
たとえば、保育園では座ってほしいので「立ち歩いたらゴチソウサマだよ」と子どもたちに伝えています。一方で、食べてほしいご家庭では「最終的に食べてくれるなら、動き回るのもしかたない」と考える保護者の方もいます。
子どもにどうしてほしいのかによっても対応が変わってきますので、ママ・パパで考えて、ご家庭でお約束を決めましょう。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」