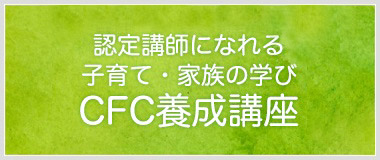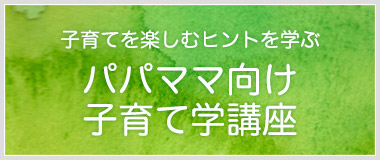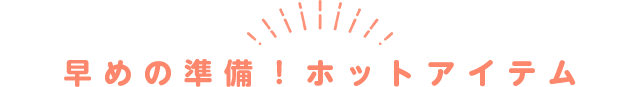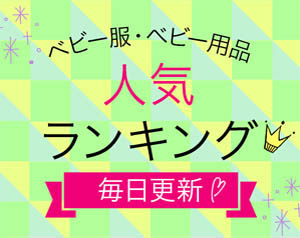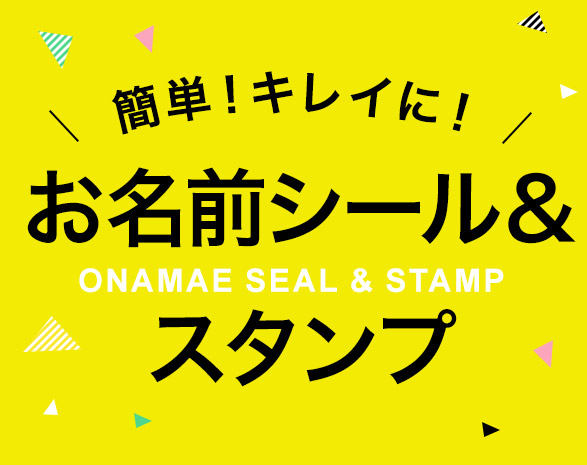ママフル365コラム “問題解決力”を一緒に育む

新学期が始まり、2ヶ月ほど経ちましたが、ようやく少しずつ生活のリズムが整ってきた頃でしょうか?
新しい環境に慣れてきた時期に、GWを迎え、生活リズムが崩れてしまい、連休明けに保育園や幼稚園、学校に行きたくないという子ども達も少なくありません。大人も少し長いお休みが続くと、元のリズムに戻るのに時間がかかりますよね。自分と環境をアジャストしていく中で、思うようにいかないことが出てきますが、子ども達も同じです。思うようにならない時、どのようにして自分の気持ちの帳尻を合わせていくのでしょうか?今回は、そんな観点から問題解決力について、お話をしたいと思います。
子ども達の毎日は問題が盛りだくさん
子ども達の一日を少し想像してみてください。朝、眠たいのに決まった時間に起きなければならず、まだ頭が動き出す前に朝の支度が始まります。時にはまだお家に居たい時でも、保育園や幼稚園に行かなければなりません。お友達と遊んでいても意見が合わず喧嘩になることもあるかもしれませんし、もっと遊んでいたいのにお片づけをしなければならない時もあるかもしれません。このように考えていくと、子ども達は日々トラブルや問題に直面しており、一つ一つ自分で考えながら行動しているわけです。子ども達にとっては、日常の生活そのものが学習の場だと言っても過言ではないかもしれませんね。人は、思うとおりにいかないとイライラしたり、がっかりしたり、どうしていくか考える時間が必要だったりしますが、特に子ども達はまだ経験が少なく、解決の方法を知らないので、泣いたり、座り込んだり、叩いたり、ものを投げたり・・・自分の気持ちを行動で表現し、気持ちの帳尻を合わせようとしているのです。
問題解決能力を一緒に学ぶ
大人の世界でも問題解決力が必要な場面は多くあります。ただ、何か問題にぶつかった時、他責にしたり、適当にやり過ごしたりして、なかなか本当の意味で問題解決ができる大人もそう多くないような気もします。問題解決能力は、歳重ねると自然に身につくものではなく、何か問題に直面した時に都度真剣に考え、対応を重ねてこそ身につく力だと私は考えています。そして、実は子どもの頃、思う通りにいかなかった時に、どのように解決をしていたかが大きく影響しているように思います。
先にお伝えした通り、子ども達は経験が浅く、言葉で上手く自分の気持ちを表現することができません。泣いて話を聞かなかったり、すねて動かなくなったりした時、みなさんはどのように向き合っていますか?まさにその時、きちんと話を聞いて一緒に考えてあげることがとても大事です。ですが、大人がよくやってしまうのが、「●●といったでしょ!」とか「●●すればいいの!」など、先回りをしてやるべきことを伝えてしまうことです。そうすると、自分で考えてやってみる、という大事な機会を失うことになります。先が見通せる大人はつい答えを教えてしまいがちなのですが、ここで一緒に学ぶ気持ちで『対話』をすることをぜひ大切にしていただければと思います。
対話の積み重ねから問題解決へ
会話は2人以上の人がお互いに話をすることですが、『対話』は会話の一つの方法で、1対1で関係性を築くためにとるコミュニケーションだと言われています。
先ほど大人になっても本当の意味での問題解決ができる人が少ない、とお話しましたが、同時に『対話』ができる人が少ないのかもしれません。前向きなコミュニケーションが取れないと諦めてしまったり、問題を放置してしまったり・・・それにより新たな問題が発生することもありますよね。
私は、問題解決力は子どもの頃から常日頃、周りの大人との対話で身についていくものだと思っています。子ども達は日常の一瞬一瞬を真剣に生きています。例えば「●●ちゃんとどんな遊びをしたの?」「お給食(お弁当)は美味しかった?」など、今日あったことを尋ね、些細なことにもきちんと向き合って話をする、時には「ママも今日お仕事大変だったよ」「パパも今日会社で違う考えの人と沢山お話したよ」など自分の話もしたりして、大人も真剣に子ども達に対峙することの大切さを知っていただきたいと思います。
子ども達は、まず感覚で様々なことを覚え身につけていきます。周りの大人も『対話』をすることを習慣的に意識していくことで、子ども達は感覚的に自分だけでなく、誰かと何かを解決していく方法を身につけていくことができます。
是非、日常の些細な対話の積み重ねが、問題解決の力につながることをイメージしながら、子ども達との対話を楽しんでいただければ幸いです。
-
 山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
- 日本女子大学大学院修士課程修了。
幼稚園教諭を経て、1995年株式会社アイ・エス・シーを設立。幼児教室や保育園運営を通じ25年以上保護者と子どもの育ち合いに携わっている。絵本を活用した独自の教育プログラム『WithBookプログラム』を、自社を中心とした各保育園にて展開し、子どもたちの「こころ」と「ことば」を育んでいる。また2008年設立のNPO法人子育て学協会にて、子育ての専門家『チャイルド・ファミリーコンサルタント(CFC)養成講座』や子育てのヒントを学べる『子育て学講座』等、各種講演・講座を開催している。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」