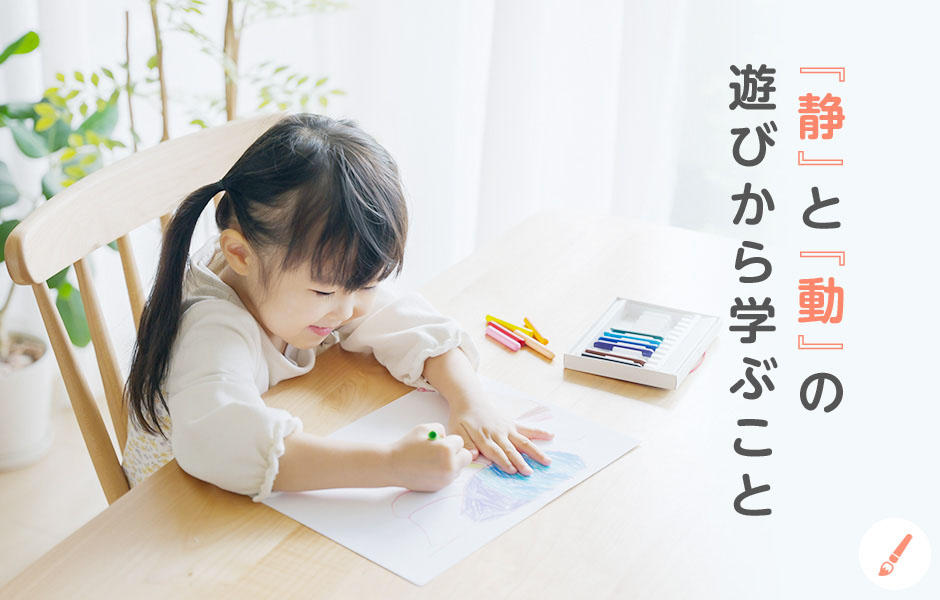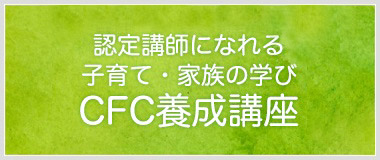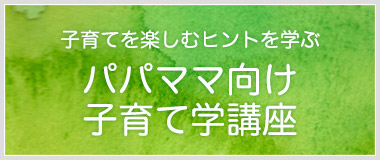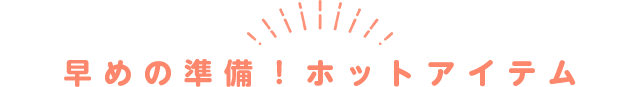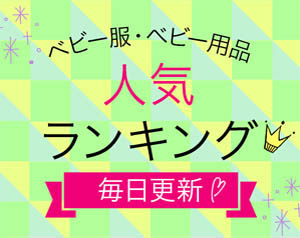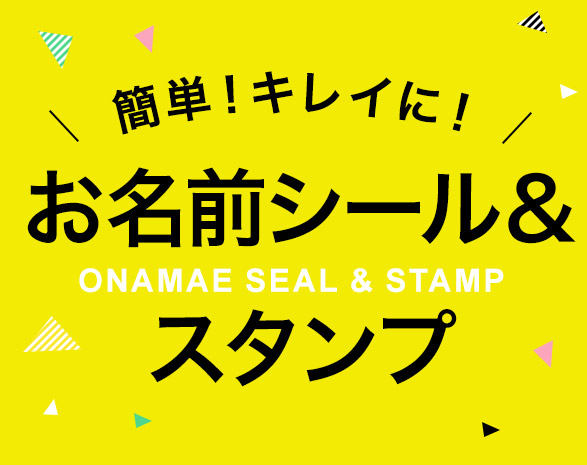ママフル365コラム 『静』と『動』の遊びから学ぶこと

今年は梅雨があっという間に終わり、例年に比べ夏が早くスタートしましたね。
コロナの状況も少しずつ落ち着き、昨年より行動範囲が広がってきている中、夏休みの計画を立て、楽しみにされているご家庭も多いかと思います。
毎日ある程度決まった流れの中で生活をしている子どもたちにとって、リズムが崩れがちになる時期でもありますが、そんな夏を子どもたちとどう過ごすか?一緒に考えてみたいと思います。
子どもたちの行動の『静』と『動』について
皆さん、ご自身が子どもの頃を思い出してみてください。学校が長い夏休みに入る頃、毎日自由に過ごせるとワクワクしたり、あれもやりたい、これもやりたいとソワソワしたりしていたかもしれません。大人になっても「夏休みにどこへ行こう?」「子どもたちとどんな経験をしよう?」と楽しみにしながら計画を立てる方も多くいらっしゃると思います。ただ、人の集まる場所へ行くことが増えるこの時期、静かにしてほしかったり、我慢をしてほしかったりする場面で、なかなか大人の思う通りにはいかないことも多く、子どもたちと非日常を共にすることは、意外と大変なことですよね。みんなが笑顔で、仲良く、ご機嫌に過ごすにはどうしたらよいでしょうか?ポイントは子どもたちの行動の『静』と『動』のバランスだと思っています。
子どもたちは、好奇心満載で興味津々の中で生きています。生活全てが遊びであり、学びです。目にするもの全てが興味の対象となり、日々、一刻一刻、新しいことを吸収しているのです。そんな中、大人は、子どもたちが感じることを大事にしたいために、ついつい子どもの気持ちを優先にしてしまいがちですが、日常の中で『静』と『動』を経験しながら自分でコントロールできる習慣が身についていたらどうでしょう。
『静』を身に着けることで得られること
子どもの遊びは、『静』と『動』、『室内』と『屋外』の4象限で分けることができます。もちろん、その子によって得意なものや集中する遊びはあると思いますが、できるだけいずれの象限の遊びも経験することが、周囲へ柔軟な対応力を身に着けることにつながるのではないかと思っています。
また、長く集中できること=得意なことだと思いがちですが、色々な経験をする中で興味関心が広がり、好きなことが変わってくるケースもあります。その中でも『静』の遊びを経験していると、待つことが比較的スムーズにできるようになります。いつも元気に走り回っていることが子どもらしいからと『動』の遊びの経験だけだと、待たなければならない場面でぐずったり騒いだり、いわゆる大人が困る行動になりがちです。でも、日頃から一緒に絵本を読んだり、お人形を使ってストーリーを一緒に想像したりして『静』の時間を楽しむことができていたら、待つ時間も子どもたちにとって、また大人にとっても、イライラせずに有意義な時間になるのではないでしょうか。
『静』と『動』のバランスを学ぶ
自分の気持ちをまだ言葉でうまく表現できない幼児期には、自分の気持ちを身体や声を使ってあらわすため、『動』の動きが表面化しやすいです。この時期に『静』の動きを習慣づけ、状況に合わせて待つことができるようになることは、子どもたちにとっても成長の大きな目安になっていきます。
大人の私たちも思い通りにいかないことと対峙することや待つことは、苦手な方も多いのではないでしょうか?まずは日常の中から『静』と『動』のバランスを意識し、うまく切り替えられるきっかけをもつことが大事なことかもしれません。大好きな人たちと夏休みを楽しく過ごすためにも、是非今から『静』を学ぶことを子どもたちと一緒に意識して備えていきたいものですね。
-
 山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
- 日本女子大学大学院修士課程修了。
幼稚園教諭を経て、1995年株式会社アイ・エス・シーを設立。幼児教室や保育園運営を通じ25年以上保護者と子どもの育ち合いに携わっている。絵本を活用した独自の教育プログラム『WithBookプログラム』を、自社を中心とした各保育園にて展開し、子どもたちの「こころ」と「ことば」を育んでいる。また2008年設立のNPO法人子育て学協会にて、子育ての専門家『チャイルド・ファミリーコンサルタント(CFC)養成講座』や子育てのヒントを学べる『子育て学講座』等、各種講演・講座を開催している。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」