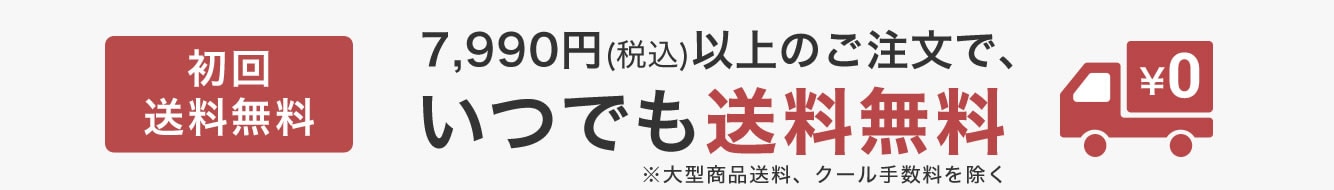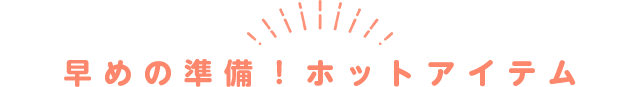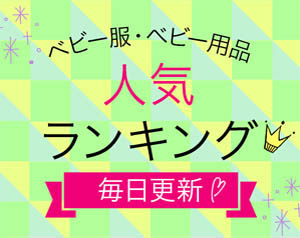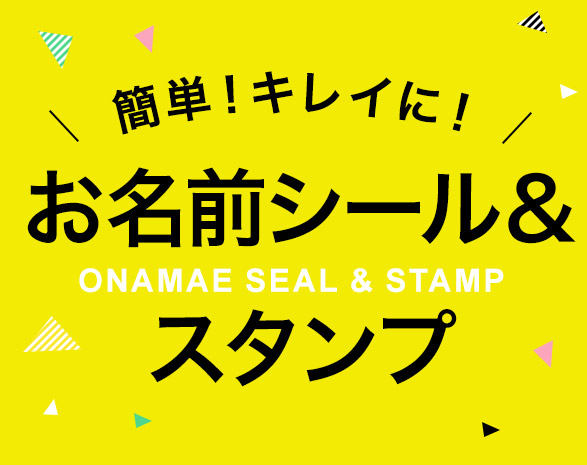ママフル365コラム 【保育園長のナルホド育児】 子どもと食事

食事は生きていく上で欠かせないもの。授乳から離乳期、幼児食や好き嫌いなどについてお話しします。
教えてくれた人:えがおの森保育園・いの 松澤園長先生
授乳期から離乳期
0歳児の授乳の時間や量は保護者と相談しながら決めます。ミルクにするか、母乳にするかにも柔軟に対応しています。授乳の際は、保育士は座って子どもを抱き、しっかりと目を見るようにします。安心してミルクを飲むことは成長にも大切だと考えているので、スキンシップを大切にしているのです。飲む量は基本的には制限せずに、規定量の中で子どもが欲しがるだけ飲ませています。
離乳食が進んでいけば、飲む量は自然と減っていきますので、これも保護者と相談しながら、1歳を目安に徐々に食事が主体になるように進めていきます。
幼児食へ?最初は手づかみ?
子どもの手や腕の骨が未発達のうちにスプーンを持たせても、うまく扱えないので、園では1歳頃までスプーンは持たせないようにしています。子どもが肘を高くあげるように誘導するおもちゃや少し重量のあるスプーンで、お豆などをすくってお椀に入れたりする遊びの中で、肘や手首がうまく使えるようになってから、スプーンを使うようにしています。これらの遊びによって腕や手首の運動機能が少しずつ高まってきます。それまでは、ご飯などは保育士が食べさせ、野菜などは持ちやすく、スティック状にし、意欲的に食べることができるようにしています。お味噌汁などは、どうしても中の具を取ろうと、手を入れたくなりますので、具を別皿に移して、つまんで食べるようにしています。指や手を動かすことは脳への刺激にもなり、子どもが「自発的に食べる」という行動を促すと思います。発達に合わせてスプーンを使っているせいか、園ではスプーンを器用に使い、食べこぼしが少ないです。
食べる時は足を床につけて
1歳児クラスからは自分で食事ができるようになっていきます。その時、気をつけているのが、子どもが足を床にしっかりつけて食事をすることです。足がブラブラしていると落ち着いて食べる事ができません。園では体の小さい子どもには、足元にお風呂マットを切って重ねた「足置き」を置くようにし、成長に合わせて、マットの枚数を調整していきます。3歳児クラスでも同じで、5歳児クラスと一緒に食事をする為、最初は足が床に届かない子どもには、牛乳パックや電話帳、まんが本等をカラー布ガムテープで巻いたものを置いて調節しています。家庭でも、足置きのあるチャイルドチェアを使ったり、ローテーブルで食事したりするなど工夫してみてください。
このお風呂マットを適当な大きさに切ったものは、姿勢を良くするのにも役立ちます。椅子の背と背中の間にマットを入れると子どもは姿勢良く食事ができます。
どうする?好き嫌い
幼児食へと移行すると、気になるのが食べ物の「好き嫌い」です。園では嫌いな食べ物を無理強いすることはしません。子どもの時に嫌いなものを無理やり食べさせられた体験は、大人になっても嫌な思い出として残ることもあるそうです。食糧事情が良い現代では、いろいろな栄養素を様々な食べ物から摂取しているので、何か食べられないものがあっても栄養不足になることはないと話す専門家もいます。そこで「今は食べられなくても、いつか食べられるようになる」と、長い目で子どもの成長を見守ることも大切だと考えます。以前、園に偏食の子どもがいたのですが、保護者と相談して見守ることにしました。
すると、その子が卒園して小学校に入ってしばらくすると、お母さんから「魚が食べられるようになりました」と嬉しい報告をいただきました。病的に痩せているわけでなければ、少し様子を見てもいいでしょう。食が細い子の場合も同様です。
ただし、食べられなくても食卓には是非並べてください。園でもその子が食べなくても、他の子と同じように盛り付けしています。いつか気が向いて食べることもあるからです。そして、子どもが一口でも嫌いなものを食べた時には「食べてくれて嬉しい」と肯定的な声をかけてあげてください。
食への興味を高める
好き嫌い、食が細い、食への興味が薄い、といった子どもたちとは、家庭菜園で野菜を作ったり、大人と一緒に食事を作ったりしてみてください。すると食への興味が高まり、これまで食べなかったものを食べてくれることもあります。
また、園では給食のメニューで使用している食材を「三色群」に分けて、体を丈夫にする食材は? 元気が出る食材は? などクイズ形式で覚えるようにしています。これらは食への興味を高めるだけでなく、大人になってもバランス良く食事をする「基礎」になると考えています。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」