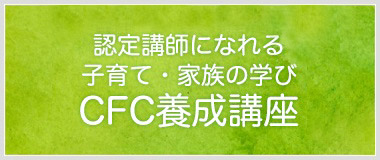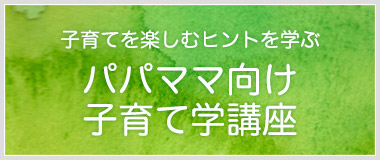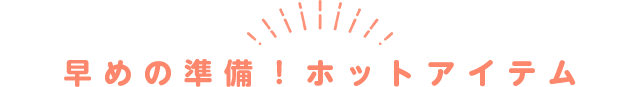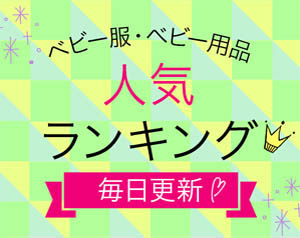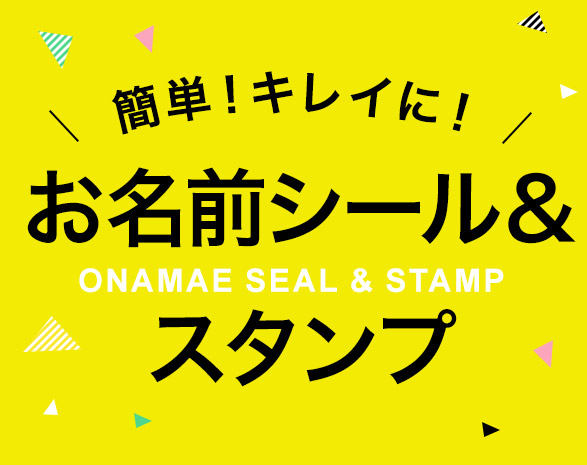ママフル365コラム 子どものおでかけ前の支度とその”時間”

「子どものお出かけ前の支度とその“時間“」について考えてみよう
4月は、何かと変化が起きる時期ですね。パパママに復職や異動があったり、子どもの入園、進級があったり。基本的に”変化“には心身共にパワーを使います。更に環境に変化が起きるとそれだけで朝のルーチンが変わり、ドタバタすることも多いのではないでしょうか?今日はこの”時間“について考えてみたいと思います。
大人の「時間」と子どもの「時間」
変化があった時にはそれに慣れるまで“待つ”というのも一つの方法です。しかし、今の世の中において“待つ”と言うこと自体がとても少なくなっているために“待つこと”に大きなパワーがかかったり、時間に追われているととてつもなく長く感じて、ついつい手を出してしまう、ということもありませんか。
今、わたしたち大人は兎角に時間に追われることが多いように思います。しかし子どもにとっての「時間」は大人の「時間の流れ方」と違うことは知っておいた方が子どもと向き合うには良いかもしれません。
子どもの時間に対する感覚
子どもに時間の感覚がつくのはかなりあとになってからです。小学校でもまず小学校1~2年で時計の読み方(時刻)を学び、時制(昨日・今日・明日)などは更にその後ですから「先を見通して今これをやる」といったことは少なくとも未就学児や小学校低学年にはなかなか難易度の高いことなのです。
「今これをやらないと後でしんどくなる」「あと5分で出るのだから、急いでやろう」などという思考を持ったり行動できるようになるには、「時制を理解し」「時間の感覚を持ち」さらに「自分がやるべきことが整理されていて」そして、「その準備を物理的にやれる身体能力が備わっている」状態です。なかなか難しいと思いませんか?むしろ大人である私も出来ていない時があります。
よくあるのが「あと5分で出るんだから支度しなさい!」と声がけしたものの、何も支度はせず、支度するはずの荷物の横にあったおもちゃでついつい遊びに夢中になってしまって、パパママが焦ってしまう・・・・というケースですね。
だからといって、親が全て手を貸してやるのは良くない、とわかっているから本人にやらせてみようと思っているのに、という声も聞こえてきそうです。
ハプニングが醍醐味のはずが焦りに
子どもがいる生活では思い通りに物事が進む、ということがそもそもあまりありません。
ちょうど出かけようと思ったら、キッチンで砂糖をひっくり返されていた、玄関を出た瞬間に「ウンチ」と言われる。せっかく着替えさせたのに、ふと目を離した隙に全部脱いでいた。
大人だけではあり得なかったハプニングが毎日起きる。それが子どものいる生活での醍醐味でもあるのですが、時間に余裕がない時にはこれらはすべて「焦り」となりそして「しんどさ」に変わります。
一方、子どもにとっては目の前で起きていることが全てであり、それらのことだけで「焦り」や「しんどさ」になることは(子どもが小さいうちは)ほとんどありません。ですから”共感“をえられない大人側はますます焦りしんどくなる、もしくは怒り心頭に発してしまうといったところでしょうか。そして一番嫌なのはその怒り心頭に発している感情だけが伝播してしまうことですね。子どもが焦るのは大人の「急いで!」「早く!」という言葉によってです。
「子どもの時間」を測る
そうならないためには、まず余裕をもった動き方をしましょうという事なのですが、そのわかりきっている事がなかなかできないのが日常の現実だと思います。また余裕を持つといってもどれくらい持てばいいのかの目安がないと、頑張れないですよね。3時間早く起きて支度ができれば焦ることもないでしょうが、ただでさえ小さな子どもがいる期間は心身の疲労も大きいですからなるべく睡眠時間は削らないでやりたいものです。
オススメなのは、親子共におだやかで時間に追われていない週末に一度平日の朝のルーチンなどをやってみることです。そして、子どもに「自分で着替える」「自分の荷物を用意する」などの役割を持たせている場合は、実際に子どもがどのような動きをしているのか、どこにどういう時間がかかっているのか、観察してみると面白いと思います。思いの外ボタンを留めるのに時間がかかっている、落ち着いてやったら3分で出来ているのに「急いで!」と声をかけてみたら急に動きがおかしなことになってスモッグが鞄にひっかかってさらにパニックになっている、など。そしてその時にわかったことの中で改善できそうなこと(ボタンを大きなものに替える等)をやったり、その時にかかった時間+αを目安に平日の朝の時間配分を考える、子どもとの合言葉を作る(「急いで!」ではなく「今日は特急列車でお願いします」とする、「何やってるの?!」ではなく「ステージ2はクリアしましたか?」と聞く等)といったことをしてみてください。
この過程で大人側が自分と子どもの時間に対する理解や流れの違いを知り気持ちの余裕が出来たり、子どもがゲームのように支度を楽しめるようになったりすることで少しでも「焦り」や「しんどさ」が減り、ハプニングを醍醐味ととらえられるパパママが増えることを心より祈っています。
-
 山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
- 日本女子大学大学院修士課程修了。
幼稚園教諭を経て、1995年株式会社アイ・エス・シーを設立。幼児教室や保育園運営を通じ25年以上保護者と子どもの育ち合いに携わっている。絵本を活用した独自の教育プログラム『WithBookプログラム』を、自社を中心とした各保育園にて展開し、子どもたちの「こころ」と「ことば」を育んでいる。また2008年設立のNPO法人子育て学協会にて、子育ての専門家『チャイルド・ファミリーコンサルタント(CFC)養成講座』や子育てのヒントを学べる『子育て学講座』等、各種講演・講座を開催している。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」