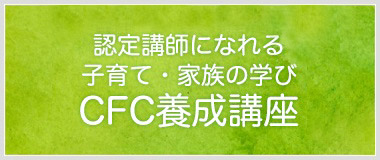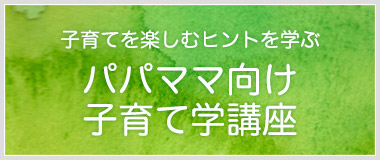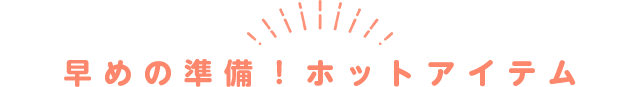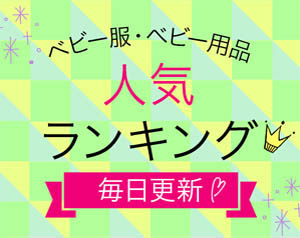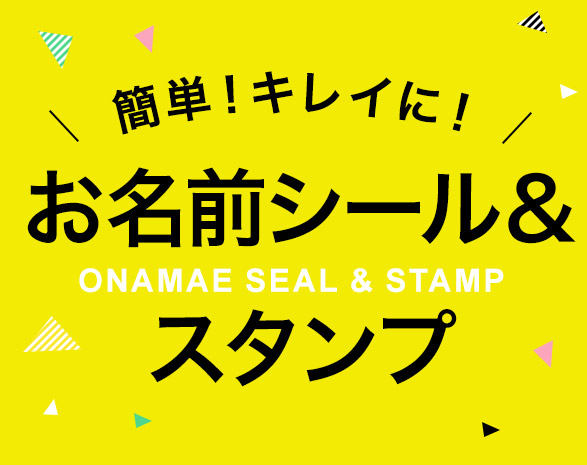ママフル365コラム きょうだいがいる家庭のお悩みについて

季節の移り変わりは早く、いつの間にか芸術の秋、食欲の秋になりました。実りの秋という言葉もあるように、沢山の美味しいものが味わえますね。今ではスーパーに行けば、一年中いろんなものが食べられるようになりましたが、ぜひ季節の食べ物を親子で楽しむことをお勧めします。旬の季節には、やはり栄養素が高いということもありますが、移り行くものを感じられる感覚や気持ちを持てると、またいろんなことの楽しみ方も広がります。四季折々の実りを頂けること、親子一緒にそれを楽しめる時間に感謝しながら、旬のものの香り、手触りも含めてぜひ全身で味わってみてくださいね。
きょうだいゲンカ
今回のテーマは、きょうだいがいる家庭のお悩みについて、です。子どもがきょうだいから一番はじめに学ぶことは、実は“理不尽さ”なのです。上の子からしてみると、ある日突然自分よりも小さい存在が生まれ、急にみんなが赤ちゃんばかりを見たり気にかけたりし始めます。一方、下の子からしてみると、世の中に出てみたらすでに自分より少し大きなお兄ちゃんお姉ちゃんの存在があり、何かあると取り合いになったり、ときには負かされてしまったり・・・ということがありますね。
お互い、そんな“理不尽な思い”を抱きつつも、お互いの関係性の中で自然と社会性や協調性を身につけているのです。
とは言え、ケンカから学ぶものがある、とはわかっていても、家の中でそれが日常茶飯事になると、親としてはついイラっとしてしまいますよね。
今日はそんな時にどうするとよいか、またなるべくそういうシーンを増やさないためにどうしたらよいか、のお話しをしたいと思います。
基本的に子ども同士のケンカに大人はできるだけ入らないことをおすすめしていますが、大きなケガにつながりそうな時や、お互いが興奮しすぎて止められない状態が続いている場合は介入せざるを得ないでしょう。
そんな時はできることなら、
1. 相手に向かって出てしまっている手や足を(叩いたり蹴ったりする前に)そっと止める
2. 低い声、かつ丁寧語で短く、求める状態を伝える 例)「もう終わりです」
3. だまって目を見る
といった静かな対応の方が効果的です。
子どもたちは興奮している状態ですので、張り合って大きな声や高いトーンで注意をしても、あまり耳には入りません。
上の子への接し方
もし、今から下の子が生まれるのであれば、もしくはまだ下の子が小さい時には、ぜひ下の子のお世話を上の子と一緒にしましょう。たとえば、下の子のおむつを買う時、離乳食を買う時など、上の子に「○○ちゃん(下の子)にはどれがいいと思う~?」と投げかけ、選ばせる、などがおすすめです。そうしていざ、下の子にそれが必要となった時には「□□ちゃん(上の子)、この前選んでくれたやつ持ってきてもらえる?」「これは□□ちゃんが選んでくれたんだよね」とお話しするのです。
また、上の子と一緒にいる時に下の子が笑ったら「□□ちゃんがいる時が、一番○○ちゃん笑うね!お兄ちゃん(お姉ちゃん)が大好きなんだね~」などと、言葉をかけてみてください。
上の子に、一緒に育児を担う一員、協力者になってもらうことで、愛情を奪われたように感じる寂しさや不安を少なくすることができます。
また、どうしてもきょうだいゲンカの時は上の子を叱りがちになりますが、意識的に上の子をケアした方が兄弟仲も穏やかになりますし、パパママの負担も減ることが多いです。
上の子は産まれた時から親の愛情を一身に受けているので、愛情を必要とする器が大きいですし、理不尽な出来事への耐性がまだついていないことも多いです。また下の子が生まれるまでは、十分に手をかけてもらえたり注目してもらえることの多い環境だったために、自分から甘えるといったことが得意ではなかったりもします。
でも、上の子は、パパママも「初めての子育て」で試行錯誤していたときに一緒に歩んでくれていた『同士』だということも忘れないでください。
最近上の子をハグしてないな、と思ったら意識してスキンシップもしてみてくださいね。
下の子への接し方
よくあるきょうだいゲンカのパターンに、下の子の方が力加減をわかっていない、もしくは自己主張が激しいなどで、上の子を泣かせてしまう、ということがあります。
上でもお伝えしたとおり、基本的には様子を見てできるだけ大人は入らない方が良いのですが、あまりにその状態が繰り返されるようであれば、一度そのサイクルを止めるきっかけを与えてあげた方が良いと思います。
この状態を止めるには、
1. 手や足が出そうな時であれば、出る前に止めて問いかける(例:出そうとした手を持ち「何をしようとしましたか?」と問いかける)
2. 今何が起きていて、どういう気持ちなのか、相手にどうして欲しいと思っているのか、を言葉で伝えられるよう促す。子どもの年齢的にまだ自分で言葉にするのが難しい場合は、問いかけたり気持ちを代弁したりしながら、少しずつ言葉で伝える練習をする。
といったことをしてみてください。
相手のことを叩いたり蹴ったり、という解決方法ではなく、「言葉で解決すること」を覚えさせていくことが大切です。
また周りの大人も、下の子には上の子ほど手をかけられない場合が多いので、コミュニケーションが雑になりがちなことに加え、下の子は小さい時から上の子を見てきたために要領が良く、周囲とのコミュニケーションにそれほど苦労せずにきていることもよくあります。
そうすると、実は自分の気持ちをきちんと言葉にし、それを伝える、というプロセスを経験しきれていないことも多いのです。
(上の子の影響で言葉を話し始める時期は早くても、実はきちんとその意味をわかっていないこともあります)
私は、「言葉を丁寧に扱えること」は、生きていく上でとても大切な力になると考えています。言語は周囲とのコミュニケーションにも大きな影響を及ぼすと共に、自分自身の思考にも大きく関係してくるからです。
家の中できょうだいゲンカが絶えないと、パパママとしては大変にストレスがたまると思いますが、一度視点を変えて、ケンカしている様子の実況中継をするつもりで観察してみてください。上の子の感情がどう動いているのか、下の子は何を言おうとしているのか・・?「“ケンカしている状態”を止めよう」と間に入って仲裁ばかりしていると、どうしても同じことが繰り返されがちです。
どういう感情やどういう状況がケンカを引き起こしているのか、という風にちょっと引いて見られるようになると、パパママの気持ちも落ち着き、そのうち子どもたちのケンカも変わってくるかもしれません。
ケンカをしながら、仲直りの仕方を学び、逞しく育っていくことにぜひ寄り添っていきたいですね。
-
 山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
- 日本女子大学大学院修士課程修了。
幼稚園教諭を経て、1995年株式会社アイ・エス・シーを設立。幼児教室や保育園運営を通じ25年以上保護者と子どもの育ち合いに携わっている。絵本を活用した独自の教育プログラム『WithBookプログラム』を、自社を中心とした各保育園にて展開し、子どもたちの「こころ」と「ことば」を育んでいる。また2008年設立のNPO法人子育て学協会にて、子育ての専門家『チャイルド・ファミリーコンサルタント(CFC)養成講座』や子育てのヒントを学べる『子育て学講座』等、各種講演・講座を開催している。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」