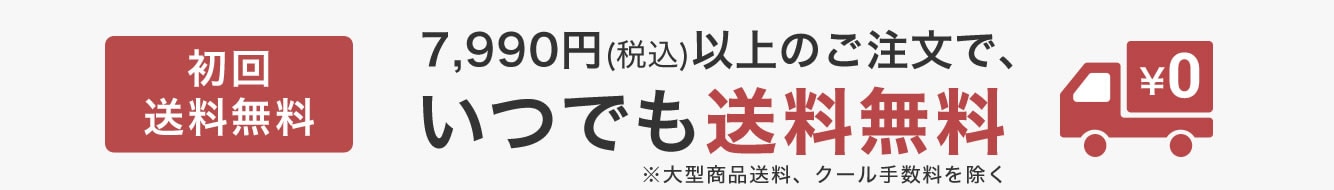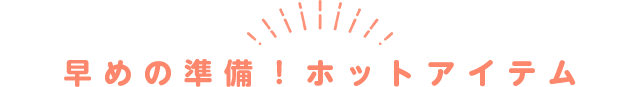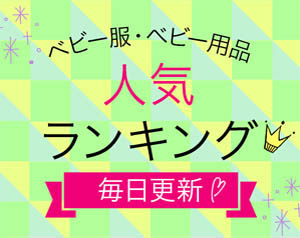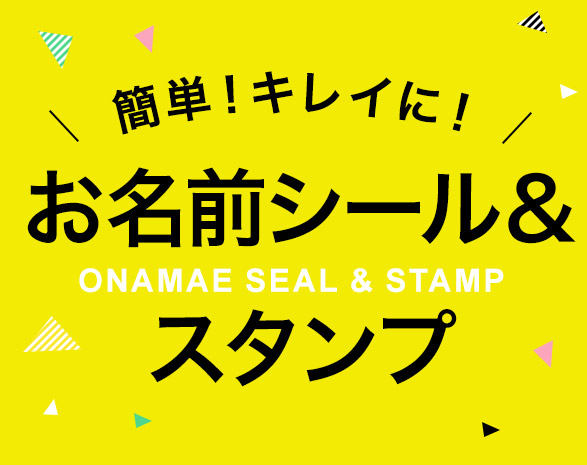ママフル365コラム 【保育園のナルホド育児】睡眠・お昼寝

園での午睡(お昼寝)を含めて、睡眠は子どもたちの心と体の成長に大切なものです。
教えてくれた人:えがおの森保育園・いの 松澤園長先生
午睡(お昼寝)の必要性
園では午睡をします。0、1、2歳児は2時間半くらいで、年齢が上がるごとに時間は短くしていきます。時々、「家で寝なくなってしまうので午睡させないで」とおっしゃる保護者もいますが、子どもは園で朝早くから夜遅くまで長時間頑張っています。午睡しないと、夕方には集中力が欠けてきたり、イライラしたり、いつもより寂しい気持ちになったりすることがあるのです。体を休める時間を取らないと、心身ともにコントロールが難しくなるので、ある程度の午睡は保育園では必要だと考えます。就学を控えた5歳児については、体力もついてきますし、小学校での生活リズムに合わせるために午睡をやめますが、眠らなくても体を休めるだけで元気が出てくるようです。子どもは午睡や休憩をとることで、お迎えの時間まで集中して遊ぶことができます。一方、お家で寝ないのも困るので、園では午後2時30分には子どもたちを起こすようにしています。
子どもをスムーズに寝かしつけるには
夜、子どもがなかなか寝てくれないと保護者も困りますよね。園では「寝かせる」のではなく「自ら寝る」ことができように、ルーティーンを決めています。ご家庭でも、パジャマに着替える、絵本を読んでもらう、寝るなどのルーティーンを決めておけば、子どもは自然と「この流れだと絵本が終わったら寝るんだな」と覚えます。
しかし、大人が隣の部屋でテレビを見ていたりすると、子どもは寝ないことも。ここは家族で話し合い協力して、子どもが寝る環境を作ってあげてください。また、大人が「子どもが寝たら家の片付けをして、明日の準備をして…」と考えていると、子どもはそれを敏感に感じ取って寝てくれないものです。そんな時は、思い切って大人も子どもと一緒に寝てしまってはどうでしょうか。その分、朝は早起きする方が大人のイライラが減るような気がします。
一人寝?添い寝?
これは国や習慣によって違うので、どちらがいいとは言えないのですが、別室で寝るような場合でも、子どもが入眠するまでは大人が側にいた方がいいと思います。保育園で過ごす子どもは保護者と一緒にいる時間がとりにくいので、子どもの気持ちを考えると、側に保護者がいると安心感が違うと思います。園では眠れない子どもの背中をトントンしてあげたり、体を撫でてあげたりすると入眠することがあります。おでこを優しく撫でているうちに眠ってしまう子もいます。やはりスキンシップは子どもの気持ちを落ち着かせるようです。
目覚める時は
園では起床のとき、「起きなさい」などと命令はしません。カーテンを開けて部屋の中を明るくして、子どもたちに光を浴びてもらいます。すると、自然に目を覚まし、起きた子どもはルーティーンに従い、次の活動の準備を始めます。すると寝ていた子どもも生活音を聞いて目覚めていきます。中には寝起きの悪い子もいますが少し待ってあげれば、コットの上でぼーっとしているうちに、自分から動き出します。
家庭でも朝目覚める時はカーテンを開けて部屋を明るくすることから始めてください。大人が支度を始める音で子どもも目覚めるでしょう。もしなかなか起きない時は「一緒に着替えようか」と声をかけ、子どもを膝に乗せて着替えを手伝ってあげてください。朝の忙しい時間にそんな余裕はない、との声が聞こえてきそうですが、急かして支度する方が、子どもは登園時に機嫌が悪くなったり、後追いしたりします。泣かれて別れるのは保護者も辛いでしょうから、ちょっと頑張って少し早起きした方が、子どもも保護者も気持ち良く一日を過ごすことができると思います。
土日の家庭での過ごし方
園では午睡をしますが、家庭では子どももリラックスして過ごしているので無理に午睡させる必要はないと思います。
ただ、土日に目一杯遊んだ子どもが月曜日に疲れていることもあります。園で昼間ゴロゴロしていたり、時には目の下にクマができていたり。平日、一緒に過ごせない分、休日に遊園地やレジャー施設に子ども連れて行ってあげたくなる気持ちも分かりますが、近所の公園でボール遊びをするだけでも保護者と一緒なら子どもは楽しいのです。遊園地などへ行くのはほどほどにして、睡眠をとって体を休め、「早寝、早起き、しっかり朝ご飯」は子どもの成長にも健康作りにも大切です。十分な睡眠は、冬場のインフルエンザ対策にも有効ですから、家族で子どもの睡眠を考えてあげてください。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」