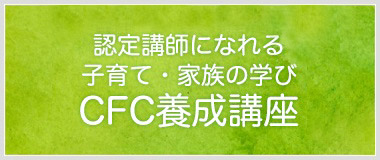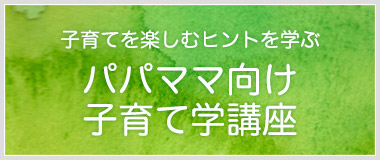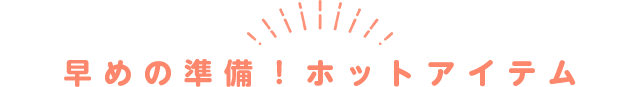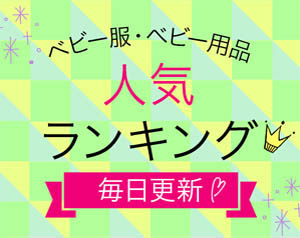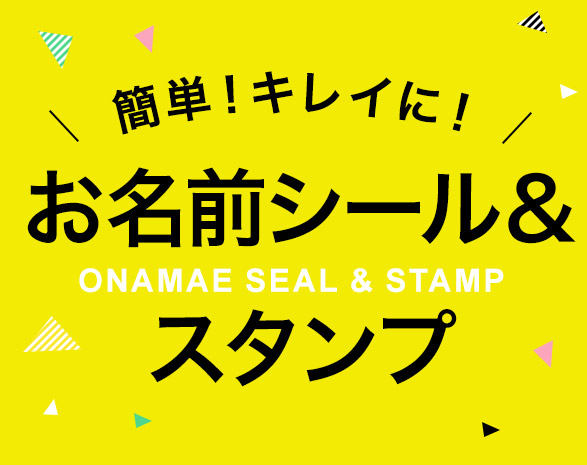ママフル365コラム 自分らしさを確立する子どもへの言葉かけの工夫

新年度のスタートから3か月経ちました。生活リズムがつかめてきたご家庭も、思っていた通りになかなかいかずに、まだまだ試行錯誤中のご家庭もあるかと思います。この時期は新年度の緊張が少しとけて気が抜けてしまいがちだったり、梅雨に入りお天気が崩れがちだったりと、何かと親子ともに体調を崩しやすい時期でもあります。
子どもが小さい間は毎日があっという間に過ぎるものです。そんな時期だからこそ、たまには予定のない日を作って、時間を気にせず家族でゆったり過ごすこともおすすめです。家の周りをお散歩して雨粒の音を聞く、露のついた植物を触る、雨上がりの花の匂いを嗅ぐ、といった五感を刺激した後、お家で一緒におやつを食べたり、時には親子でお昼寝して心身を休める時間を持ってみてくださいね。
子どもへの「言葉かけ」―”褒める”
“褒める”とは何でしょうか?
国語辞典をひくと「立派である、良いことであるとして言う、讃える」(小学館)「物事のすぐれているのを認め、それを良く言う。称賛する」(旺文社)などとあります。これだけを見ると『子どもを褒める』というのはなかなか難しいことのようにも思えてきます。
私がよくパパママにお伝えしているのは、“プロセスでの見えた事実を子どもに伝える”、そして“その時に感じたことを合わせて伝える”ということです。
例えば、お友達と一緒に遊んでいて、おもちゃを譲れた時。
「おもちゃを譲れたんだね。優しいなあ、って嬉しくなったよ。」
園で作った制作物も、作っている過程は見られなくても、持ち帰ったものを見て「初めて紫色を使ったんだね!ずいぶん長い線も描けるようになったんだねぇ!びっくりしたよ。」などと具体的に伝えられるといいですね。
もしかすると大人が考える“称賛”“立派”といったイメージとは違うかもしれませんが、子どもは、言っている大人の表情や声のトーンで“褒められている”ということだけでなく、見てもらえている、という安心感を得られます。
気を付けたいのは、最後の完成形や結果だけを見て「すごいね」「上手だね」を連呼してしまうことです。大人が発する「すごい」「上手」は、子どもから見ると“すごくなければいけない”“上手じゃなきゃだめだ”と、言われているようなもので、大人からみれば、無意識の中に大人の基準にあわせた行動をあてはめて、行動を評価していることも少なくありません。
“何が”良かったのかという部分がわからず、言葉だけで繰り返すと、「大人の評価を気にする」「大人が気に入る言動を取る」といった行動につながることがあります。
それに慣れてしまうと、評価軸がわからない時に混乱したり、自分の興味がわからなくなって何をして良いのか決められなくなったり、ということにもつながりかねません。
「すごい」「上手」を使わず、本人に感想を伝えるのは実はとても難しいことかもしれませんが、日々意識しながら練習しておくことをお勧めします。
実際に言葉をかけてみて、子どもの様子をよく観察し、試行錯誤してみてくださいね。
事実を伝えることで、本人からこだわったポイントや、その時の想いなどが出てくることもありますよ。
子どもへの「言葉かけ」―”叱る”
褒める”と同じく難しいのが“叱る”ですね。
まず、普段叱っている内容はどういうことがあるか振り返ってみてください。
冷静な時に振り返ってみると、意外と「これ叱らなくてもよかったかも」ということも出てきたりします。頭ではわかっていても止められない時もありますよね。
そんな時は後からでもいいので、「さっきは言いすぎちゃったね」と伝えましょう。
叱る時のポイントを今日は3点お伝えします。
①子どもの身体を触る
叱っているうちについついヒートアップしてしまうというのは、自分が興奮している声が耳から入ってきて、更に興奮するというスパイラルに入ってしまうのもあるでしょう。そうならないためにも、子どもが小さい時は、叱る際に子どもの身体を触る(立った子どもの両腕を持って話すなど)ことをしてみてください。
スキンシップは大人も子どもも落ち着く効果があります。
②低いトーンで、丁寧語
子どもに大きな声で叱ることを繰り返していると、本当に危険な時などに大きな声を出しても子どもに届かなくなります。また、激しい口調で叱りつけるよりも低いトーンや丁寧語で伝えた方が子どもには伝わりやすく、また“まずいぞ”と思わせる効果は大きいです。
③「目を見てごめんなさい」にこだわりすぎない
「きちんと目をみて、ごめんなさいでしょ!」と大人が子どもを諭している、叱っている場面を時々みかけますが、子どもの様子を見て反省しているな、理解しているな、と思ったらある程度のところで「次は言いましょうね」と切り上げましょう。
大人でも本当に悪かったな、と思った時に改めて「ごめんなさい」と口に出すのはなかなか勇気のいること。これは子どもも一緒です。ただでさえ言うことのハードルが高いのに、必死で「ごめんなさい・・・」と声に出したら「もっとちゃんと!」と更にハードルをあげられる。これが続くとますます「ごめんなさい」が言えなくなっちゃいそうですよね。叱る目的は「ごめんなさい」を言わせることではなく、何をしてはいけなかったのかを理解し、繰り返さないことです。相手にきちんと謝罪する必要がある時であれば、少し時間を置いて落ち着いた時に一緒に行くなどでも良いと思います。
褒める目的・叱る目的とは
子どもを育てる過程で褒めること、叱ることはいずれも大切なことだと思います。
ただ、その目的はいずれも、(親がいない場面でも)周りの人に可愛がられ、周りの人と時にぶつかりながら切磋琢磨しつつも、その子がその子らしく自分の道を切り開いていくことです。そう考えると安易な「上手だね」という言葉よりも、「それが好きなんだね」と伝えることで、幼い頃から本人が自分らしさに気付き、それを得意にしようとする力が働くこともあります。
同じように叱るよりも「これを違う時にやったらどうなったと思いますか?」と問いかけたり、違う立場の人の気持ちを想像することで思いやりのある子に繋がっていきます。その目的から考えると、いろんなアプローチをした方がより深く感じたり考えたり出来ると思います。夫婦間で「遊びの時」「食事の時」といった場面で切り分けたり、「初めに叱る役」「繰り返した時に叱る役」といった役割で分担してみてもいいかもしれませんね。
パパママそれぞれのキャラクターや子どもとの相性もあると思うので、是非具体的なシーンを思い出しながらご夫婦で話し合ってみてはいかがでしょうか?
-
 山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
- 日本女子大学大学院修士課程修了。
幼稚園教諭を経て、1995年株式会社アイ・エス・シーを設立。幼児教室や保育園運営を通じ25年以上保護者と子どもの育ち合いに携わっている。絵本を活用した独自の教育プログラム『WithBookプログラム』を、自社を中心とした各保育園にて展開し、子どもたちの「こころ」と「ことば」を育んでいる。また2008年設立のNPO法人子育て学協会にて、子育ての専門家『チャイルド・ファミリーコンサルタント(CFC)養成講座』や子育てのヒントを学べる『子育て学講座』等、各種講演・講座を開催している。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」