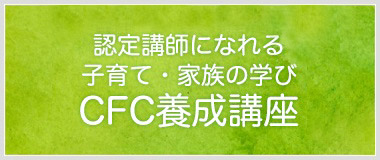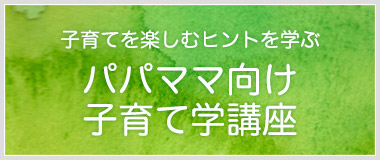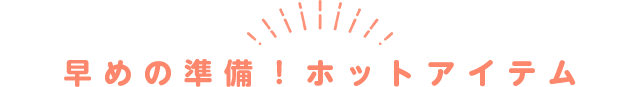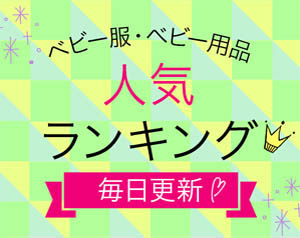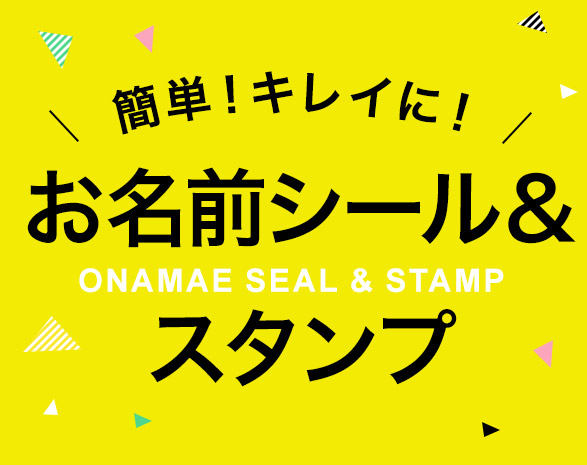ママフル365コラム 子供の「強み」の見つけ方「子供の観察方法・伸ばし方」

あっという間に一年の半分以上が過ぎ、じっとしていても汗ばんでくる季節になりました。子どもは大人よりも汗をかきやすいため、こまめな水分補給に気を付けたいですね。
幼稚園が夏休みで毎日子どもとの時間の過ごし方に迷われるパパママや、保育園に通っていて夏休みらしいことをどう実現しようかと迷われるパパママなど、それぞれのご家庭によって楽しみもありつつ、悩ましい面もあるかもしれません。今年の夏は今年しか経験できませんので、泣いたり笑ったり驚いたり、沢山の感情が生まれるような思い出に残る夏にできるといいですね。
子どもの「強み」の見つけ方
「お子さまの強みは何ですか?」と聞かれた時、すぐに答えられますか?
ご存知の方も多いかと思いますが、強みと弱みは表裏一体です。弱みだと思っていたことも、場面が変わると大きな強みになります。そう考えると強みというのはそもそも何でしょうか?
強みとは、ある状況において有利に働いたり、頼りになるその子の性質だと考えています。
強みがわかっていると、それを活かした場面や活動を増やすことができ、自己肯定感を持ちやすくなったり、前向きな人間関係を作るきっかけになったりもします。また、自分自身の好きなことを特技にできたり、それによって達成感や充実感を味わえる瞬間が増える、ということもあるでしょう。
強みを見つけるには、まずは子どもの様子を観察することから始まります。
どんな時に夢中になっているのか、どんな時に静かになるのか、嬉しそうにするのか、悲しそうにするのか、など、まずは顔の表情をはじめとして、全身の様子をよく見てみましょう。
そうすると、とにかくその子の特徴がいろいろ見えてくるはずです。
内容によっては「これはむしろ弱みじゃないかな」と思えるようなことも出てくるかもしれません。でもそれは、上でもお伝えしたように裏返すと強みになることです。
たとえば、砂場にいくとパパやママの声も全く聞こえない様子でずっと遊んでいるAくん、その砂場にくるお友達や犬などにいち早く気付き声をかけたり一緒に遊んだりするBちゃん、砂場の横に立ってそれらの様子をじっと見ているCちゃん、砂場から出て自分でブランコやすべり台で遊んでいるDくん。いろんな子がいます。
これらの場面ではどの子にもその子の強みが表れていますよね。Aくんは集中力や探求心が強いと思われます。Bちゃんは察知能力やコミュニケーション力が高いでしょう。Cちゃんは人に惑わされることなくマイペースで観察力に長けているかもしれません。Dくんは自由な発想力や行動力が見られますね。
このように、“その子らしさ”が強みとして活かせる場面であれば、「今日は、15分も集中して砂場で遊んでいたね」「今日は砂場にどんなお友達が来た?よく観察していたみたいだから教えて」などと本人に伝えてあげられると、本人も自分の強みを理解していき、さらにそこが伸びていくきっかけにつながると思います。
習い事の選び方
最近は習い事の幅も本当に広がっていて、何をさせようかと迷ってしまうパパママも多いのではないでしょうか?
習い事を始めるきっかけや何を選ぶかは、子どもが小さい時はパパママの意向が反映されることもあるでしょう。それ自体は悪いことではないと思いますが、先ほど触れたその子の強みが活かせる場面があるか、その子らしさを受け入れてくれる場所・先生か、というのは選択肢をあげるときの一つの観点として入れてみてもいいですね。
また、習い事を選ぶ際に「動」と「静」それぞれをバランス良く考えるのもお勧めです。
「動」というのは身体を動かして発散したり、自分の身体をうまくコントロールできるようになることが目的のもので、多くのスポーツ系の習い事がこちらに当てはまります。
一方「静」というのは、集中することや探求することを中心としたもので、ピアノなどの芸術系の習い事やそろばん、お習字などの習い事がこちらに当てはまります。
大人になりさまざまな壁にぶつかった時、リフレッシュしたい時などにも、「動」「静」いずれの発散の仕方も自分で持っているといいですね。
子どもの時に始めた習い事が大人になるまで続くかはわかりませんが、考え方として一つ知っておくと、パパママのストレス発散・リフレッシュ時の参考にもなるかなと思います。
時々、元気なお子さまのパパママで「エネルギーが余っているから」と「動」の習い事ばかり始められることがありますが、そうすると身体を動かすことで発散、切り替えをする方法しか学べず、ますます動きが活発になってしまうということがあります。
「静」の時間や場所を持ち、集中したり探求することの楽しさを学ぶことは、実は活発な子どもほど必要としているかもしれません。
走り回るのが大好きな子どもが突然机の前で何時間もじっと座っている、といったことは確かに苦痛ですが、子ども向けの教室では程よく身体も動かしながら実施するプログラムになっていることが多いので、そういった時間や場所に触れることも是非トライしてみてくださいね。
また、子どもの可能性を広げてあげたいのが親心ですが、多くなりすぎるのは避けたいところです。大人でも毎日分刻みのスケジュールで次から次と課題を与えられると、疲れてしまってなかなか新しいことも頭に入ってこなかったりしませんか?
これは子どもも同じです。いくつもの習い事をしても結局その内容が身につかないようではもったいないですね。きちんと身につけようと思うと、幼児期には「静」と「動」の習い事を一つずつ、というのが理想かなと思います。親子ともに習い事に行くことで疲れてしまって、せっかくの親子の時間に子どもと向き合えなくなってしまったりしたら元も子もありませんね。
特に子どもが小さい時の習い事は、ベースとなる心身の健康や生活リズムが整った上でやることで、効果的な知識や技術の習得が期待できるものです。
お子さまの特性や家族の状況などを見ながら、焦るのではく、親子で一緒に新しい出会いや刺激を楽しめる状態でスタートし、継続していけるといいですね。
-
 山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
- 日本女子大学大学院修士課程修了。
幼稚園教諭を経て、1995年株式会社アイ・エス・シーを設立。幼児教室や保育園運営を通じ25年以上保護者と子どもの育ち合いに携わっている。絵本を活用した独自の教育プログラム『WithBookプログラム』を、自社を中心とした各保育園にて展開し、子どもたちの「こころ」と「ことば」を育んでいる。また2008年設立のNPO法人子育て学協会にて、子育ての専門家『チャイルド・ファミリーコンサルタント(CFC)養成講座』や子育てのヒントを学べる『子育て学講座』等、各種講演・講座を開催している。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」