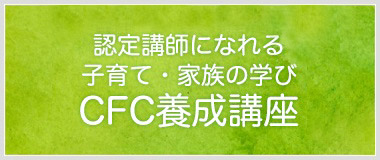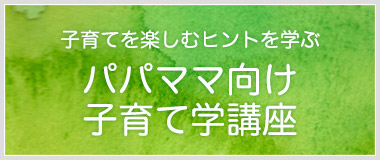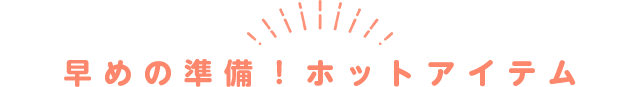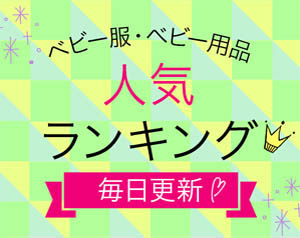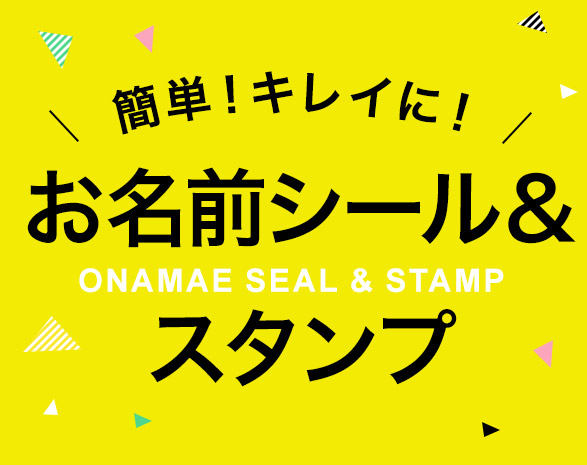ママフル365コラム 入園・進級シーズンの「親と子どもの気持ちの整え方」

変化が多い4月に向けて、この時期は親も何かと気忙しいですね。
自分の中のなんとなくの不安と期待を整理することで、心も落ち着いてきます。
ぜひ焦らずにいきましょう。
2月といえば、保育園の入園結果の通知が届いたり、進級が目の前になってきて、嬉しい、寂しい、不安、焦りなど、まさに悲喜こもごも複雑な気持ちが入り乱れる月だな、と思います。子どもにとっても、「変化」というのは大きく成長するきっかけになると同時に、「不安」な気持ちを引き起こす要因ともなりえます。今回はまず、この「変化」が起きがちな4月に向けて、子どもを持つ親が心づもりしておくことで、まずは自分たちが”楽“になるヒントをいくつかお届けしたいと思います。
親の「変化」にご自身は気付けていますか
保育園の入園、進級、子どもの成長など、様々な変化がある中、皆さんはまずご自身の「変化」に気付けていますか?
環境や子どもの成長など、周囲の変化を自分がどう受け止めていて、それに対して自分はどういう気持ちを持っているのか、どうしたいのか、ということを、変化が大きい4月を迎える前に、パートナーや祖父母の方などと話したり確認したりする場を一度設けることをお勧めします。人間は様々な感情を持つ生き物ですから、どの感情が良い悪い、ということはありません。不安やイライラも湧き上がってくるものですから、それ自体を抑える、といった無理な動きをすると余計にその感情を膨れ上がらせることがあります。「あーイライラしてるなー」「あー、不安ですごく悲観的になってるな」ということを自分で気付けるようになる、もしくはそれを指摘してもらう仕組みを作っておけるといいですね。
家族の中で、仕組みを作る
家族というのは、誰かと誰かの意思を持ってスタートのきっかけができますが、その後も健全な形で続けていこうと思うと、その時の状況を把握する仕組み、それぞれが役割を担っている状態が必要です。この仕組み作りや役割分担を「変化」が激しい4月以降にやると、家族の中で大きな衝突やひずみになりかねないので、その前にやっておくことをオススメします。仕組みと言っても簡単なものでいいのです。まずは、お互いの心身の状況をきちんと把握できるルールとそれに伴って派生することの取り決め。たとえば、心身ともに限界がきそうな時には、パートナーにこの絵文字を送り、その日は早めに寝て復活に努める、その日はもう片方が残りの家事をやる、など。もしそれが続くようであれば、そもそもの生活スタイル、分担の仕方を見直す、なども必要ですね。逆に、本人は気付いていないけれど、「大変そうだな」「しんどそうだな」と思ったらこの絵文字を送って、自分で気付いてもらうきっかけにする、というのがあってもいいかもしれませんね。
何事もやってみないとわからないので、細かいことを決め過ぎるとそれに縛られてしまいかえって自分たちがしんどくなることもあります。大切なのは、お互いの状況をお互いがわかり、「思いやれる状態」を保つために必要な仕組みです。

誰でも担える状態が一番つよい
この数年で、大きく旧来の性差による役割分担の意識も変わりつつあると思います。
家事・育児を、今夫婦のどちらかがメインでやっている場合は、それを周りが認めつつ、そのスキルをシェアしてみんなができるようにしていくと、長い目でみると家族全員が楽になります。
例えば、「この子はこの服がお気に入りだから、朝ぐずってお着換えをしない時はコレ!」などの情報をたくさん知っているママと、そうではないパパとで、朝の登園準備にかかる時間が倍近く違う、なんていう話もあります。そしてその“お気に入りの服”はどこで買えるのか、ということもパパが知っていれば、必要があれば自分で買ってくることも可能です。
子どもでいうと、“お手伝い”がまさにそうですね。子どもが小さいからまだ、と思うかもしれませんが、例えば保育園に持っていくおむつに自分の名前のスタンプを押す、なんてことは子どもにとっては遊びにもなり楽しくできますよね。
嬉しい気持ちや楽しい気持ちと共に、生活するために必要な家事も家族みんなで少しずつシェアしていった方が、新しいやり方を発見できるきっかけにもなります。
もちろん家族それぞれでシェアのやり方や分担の割合は違うので、理想を掲げてそのギャップで悩むのではなく、それぞれの夫婦で試行錯誤しながら“自分たちらしいやり方”を見つけていくのが一番だと思います。
またその時に、保育園の先生や小児科の先生など、子どもの専門家と呼ばれる人たちに普段から相談したり、意見を聞いたりして、やりとりを夫婦の中だけに閉じずにやる、というのもお勧めの一つです。
人間二人だけで向き合っていると、どうしても息が詰まる瞬間もあります。子どもがその子らしい状態を出せるためには、周りの大人が安定していることがまず大切です。
“頑張ってなんとかする!”ではなく、必死で走りつつも、一緒にその必死さをわかち合い、相談し合える仲間を作って、孤立化せず周りと共に楽しめる状況が作れるといいですね。
-
 山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
- 日本女子大学大学院修士課程修了。
幼稚園教諭を経て、1995年株式会社アイ・エス・シーを設立。幼児教室や保育園運営を通じ25年以上保護者と子どもの育ち合いに携わっている。絵本を活用した独自の教育プログラム『WithBookプログラム』を、自社を中心とした各保育園にて展開し、子どもたちの「こころ」と「ことば」を育んでいる。また2008年設立のNPO法人子育て学協会にて、子育ての専門家『チャイルド・ファミリーコンサルタント(CFC)養成講座』や子育てのヒントを学べる『子育て学講座』等、各種講演・講座を開催している。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」