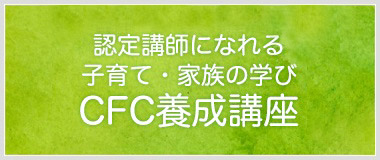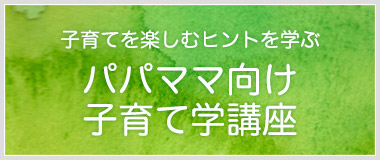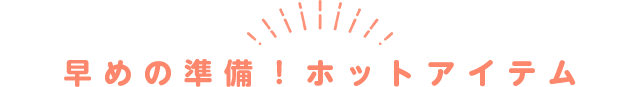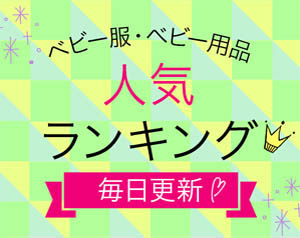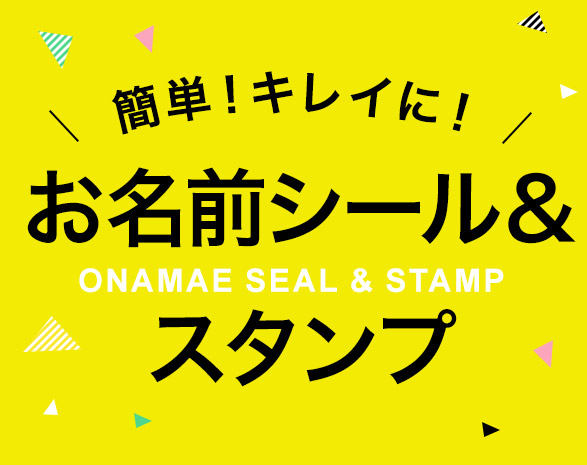ママフル365コラム ファミリービルディング

今年は多くの方が予想もしていなかった一年になったのではないでしょうか。年初に目標を掲げた方もいらっしゃるかと思いますが、この大きな変化の中で達成できなかったことも多くあったかもしれません。ただ、一見すると「できなかったこと」が山積みのように感じますが、当たり前だと思っていたことを見直したり、これまでできなかったことをできるように加速させる「変化が起きた」年と、見方を変えることもできるのではないでしょうか。これを機に、“通勤”や“ハンコ”の意味を改めて考え見直した企業様も多いようですし、オンライン授業を実施する学校も増えてきました。どちらも長年言われ続けていたことですが、本格的に検討・実施するフェーズに入ったようです。個人の方でも、改めて”働く”ことの意味や意義を考えたというお話を聞く機会も少なくありません。社会も個人もどのように変化すればよいか、明確な答えはわからないですが、数年先、数十年先、さらに先の未来において、少しでも生きやすく、自分らしく過ごせる社会を子どもたちに残してあげられるよう、第一歩を踏み出したと考えたいものです。
今月号は一年の締めくくりとして、読者のみなさまには”家族”という単位で改めて考えていただく機会にしたいと考えました。年初に自身の抱負や目標を立てる方は多いと思いますが、「家族」の場合はどうでしょうか? 当たり前のように「家族」と言う単位での会話が増えるといいなあ、という思いも込めて、お伝えしたいと思います。
責任のバイアス
家族の中では様々な“パートナー”が生まれます。一番わかりやすいのは夫婦という形態で、第一子が産まれると、一緒に「子育て」を試行錯誤するパートナーだったりもしますよね。親子もやる事柄によってはパートナーとなりえます。一緒にペットの世話をするパートナー、近所のお買い物に行くパートナーなど・・・
そのパートナーとの関係性が上手くいっていると、やろうとしていることをより楽しく感じたり、思わぬ成果が出たりします。でも中々そうはいかないのが実情ではないでしょうか。
心理学者のマイケル・ロスとフィオーレ・シコリーの「責任のバイアス」という研究を少しご紹介したいと思います。夫婦に対して「夫婦関係を維持するために、あなたが実際に担当している割合は何パーセントでしょうか?」と投げかけた結果、4組に3組のカップルが二人の数字を合わせると100%を大幅に超える、というものです。人は自分の貢献を多く見積もり、他人の貢献を低く見積もってしまいがち。これは不遜だ、傲慢だ、という話の前に、情報量が圧倒的に違うということを理解したいですね。自分がやったことは全てわかりますが、他人がやったことはどれほど頑張っても全てを把握、理解することは無理です。そうなるとできる事は一つ。自分が知っていることはごく一部だな、一つの側面でしかないな、と思い出すことです。子どもだって、家での様子が全てではありません。幼稚園保育園ではとても頑張っている分、家では甘えてしまったり気が抜けたりすることもあるかもしれませんね。
アンコンシャスバイアス
最近、社会的にも話題になっていますが、「アンコンシャスバイアス」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。無意識の中で持っているモノの捉え方のゆがみや偏りのことです。家族の中でも、父親だから、母親だから、男だから、女だから、といった性区別で決めていることがあったりしませんか?父親だから大黒柱であるべき、母親だから世話をしなければいけない、男の子だから強くなって欲しい、女の子だからおままごとが好きなはず・・・そういった自分の中に無意識にある“べき”“はず”という概念は誰にでもあるものです。誰にでもあり、完全になくすことはできないものですが、それに気づいているかどうかで楽になれることもあります。家族の中で担っている役割分担が本当にそうある“べき”なのか、子どもに叱っていることは自分のこうある“べき”がもとになっていないか、定期的に見直す機会があるといいですね。
家族内の役割というものは本来(子どもが小さい時は特に)誰もが担えるのが一番です。そして好きな人がやるのが一番よいのです。自分が好きではない、苦痛なことがあったら、家族に「実はちょっと苦手なんだけど、誰か一緒にやってくれる人いませんか?」と勇気を出して話してみてはいかがでしょうか?思わぬ解決方法が見つかるかもしれません。
家族内ハーモニー
家族といえども、モノの見方も考え方も表現の仕方も様々。違う意見があるとついぶつかってしまうこともあると思います。でもその“違い”が貴重であり、そして子どもの成長には欠かせないことです。色んな人がいる、様々な考え方がある、たくさんの感情がある、ということを身近な人から学べる子どもはとても幸せです。時に不協和音になることもあるとは思いますが、違う意見を戦わせるのではなく、対話により一つ一つの音が和音となり、ハーモニーを奏でることができる、と考えています。定期的に家族で話し合う機会、同じ経験を共有する時間があると、そのハーモニーを感じることが増え、豊かな心が育まれるのではないかと思います。
家族の形に正解やGoalはありません。それぞれの家族で、自分たちの形、自分たちのハーモニーを作り出せると私は信じています。この記事を読んで、是非新年には「家族」の抱負についてお話をされるご家族が増えますように。よい年をお迎えください。
-
 山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長
- 日本女子大学大学院修士課程修了。
幼稚園教諭を経て、1995年株式会社アイ・エス・シーを設立。幼児教室や保育園運営を通じ25年以上保護者と子どもの育ち合いに携わっている。絵本を活用した独自の教育プログラム『WithBookプログラム』を、自社を中心とした各保育園にて展開し、子どもたちの「こころ」と「ことば」を育んでいる。また2008年設立のNPO法人子育て学協会にて、子育ての専門家『チャイルド・ファミリーコンサルタント(CFC)養成講座』や子育てのヒントを学べる『子育て学講座』等、各種講演・講座を開催している。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」