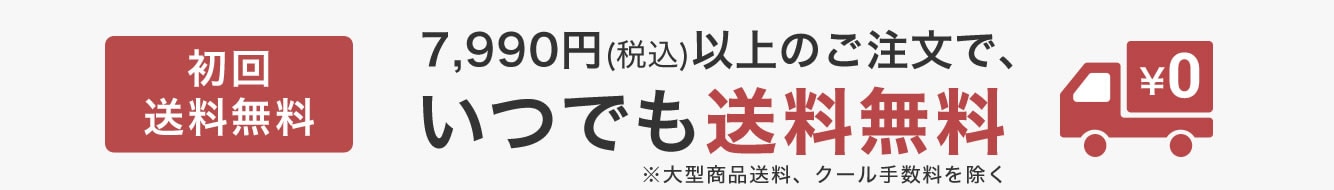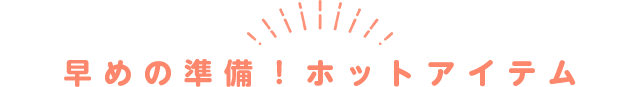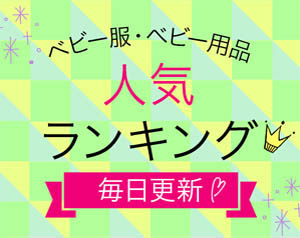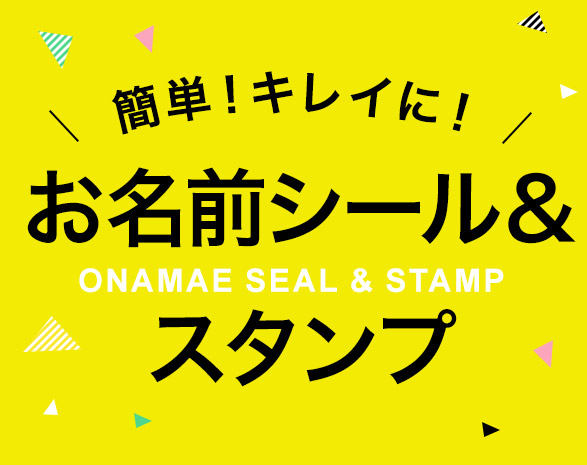ママフル365コラム 【保育園長のナルホド育児】「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること

「生きる力」という「非認知能力」をどうやって伸ばしていくか、保育園の先生に教えてもらいました。
教えてくれた人:えがおの森保育園・せんごく 堤園長先生
新学習指導要領にも盛り込まれた非認知能力。非認知能力はやりぬく力や、他者を受け入れる力のこと。「生きる力」とも言える非認知能力は、子どもの主体的な遊びを通して伸びていきます。そのため、園では子どもたちの「やりたい気持ち」を伸ばしていくように心がけています。
「生きる力」は家庭でも伸ばせる
園では非認知能力を伸ばすような保育を心がけています。では、家庭で非認知能力を伸ばすにはどうしたらいいでしょうか? その方法をご紹介します。
先回りしない
子どもが失敗しないように、つい先回りして親がやってしまう、障害を回避してしまうことありますよね? それでは、子どもの生きる力は伸びません。失敗して居心地の悪い思いや、悔しい思いをすることで「どうしたら失敗しないのだろう?」と子ども自身に考えさせます。園でも散歩などで子どもが転びそうになった時はつい手を引いてしまいますが、転んだほうがいい経験になったのかしら? と思うことも。身体的な危険の無い範囲で子どもにやりたいことをやらせてみましょう。
やりたいことを子どもが決めて、大人は見守る
園では、子どもたちに決めさせる場面をたくさん作っています。そして、自分が決めたことを途中で投げ出さないように見守ります。これが責任感や達成感につながるのです。「自分で決めた」という動機があると、子どもはがんばるもの。家庭でのお手伝いを自分で決めてやらせるのもいいでしょう。投げ出しそうになったら、励ましてあげてください。それでもうまくいかない時は、どこが困っているのか子どもに聞いてみます。そして、そこだけ一緒にやってみるのもいいでしょう。しかし、助け過ぎないように注意してください。
例外を作らない
大人は決めたことに、都合良く「例外」を作ることがあります。これは子どもが混乱します。夜、子どもに何冊も絵本を読んでとせがまれて困るといった相談を受けることがあります。これも毎晩2冊まで、と決めたら大人はそれを守り抜くこと。子どもが駄々をこねてもそれ以上は約束なので読みません。そして旅行先でも絵本を読みます。それは毎晩読むと決めたから。例外を作ってはいけません。すると子どもは「約束は守るもの」という社会的素養が身につき、「生きる力」へとつながります。
全体を褒めるより、頑張ってできたことだけを褒める
最後まで出来きたら褒めてください。出来上がり具合を褒めるよりも、「出来た」ことを褒めてあげてください。上手か下手かという大人の評価を押し付けてはいけません。途中投げ出しそうなったけれども諦めなかったところなど、過程を褒めることは、子どもの承認欲求を満たします。すると成長してから「答えを出せばいい」ではなく、「答えを見つける過程」を楽しむようになるでしょう。
口や手が先に出そうになったら、「10」数える
見守ることは難しいもの。大人が手を貸せばすぐに終わることでも、子どもに任せていては時間がかかってしまう。そこで園では、つい「こうしたら?」と言いたくなる時、「ちょっと貸して」と手を出したくなる時、まず「10」数えることにしています。そして子どもが今、何ができないのか、何に困っているのか観察します。そこで、声をかけた方がいいのか、そのまま黙ってやらせた方がいいのか、判断するようにしています。
子どもの主体的な行動を待つのは根気が必要です。特に朝は大人にも時間的な余裕がないので、手や口を出してしまいがち。でも、子どもに自ら考え、行動させるようにした保護者はやがて朝の時間が楽になったと言います。ガミガミ言わないほうが結果的に早く支度ができたという保護者の方もいらっしゃいますよ。
新学習指導要領を始め、教育の世界で非認知能力の重要性が注目されています。しかし非認知能力とは何かを考えていくと、「自分で考え、行動する」「他者(お友だち)を受け入れ仲良くする」など、保育の現場では以前から大切にしてきたことと重なる部分も多いのです。
これからも家庭と園が一緒になって、子どもたちの「生きる力」を育んでいきましょう。
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」