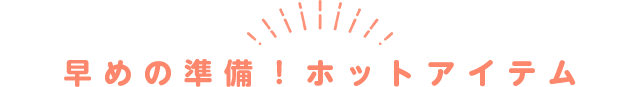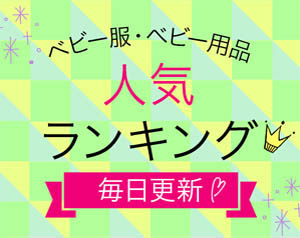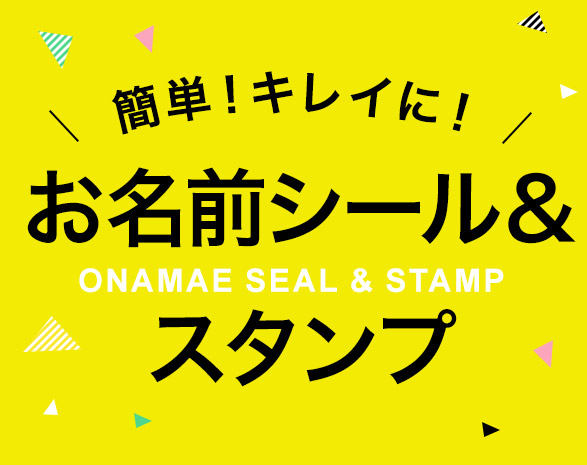ママフル365コラム 【保育園長のナルホド育児】子供靴の選び方

教えてくれた人:千趣会チャイルドケア スーパーバイザー 松澤先生(えがおの森保育園・いの 元園長)
「立てば歩めの親こころ」ということわざがありますが、まさしく親ってひとつ何かができると次は‥と期待してしまいますよね。歩き始めたお子さんの“可愛い姿は目に入れても痛くない”ほどです。
いよいよ、歩き始めると、どのような靴を選んだらいいのかな・・など“ワクワク”したり反面悩んだりもしますね。
また、成長するにつれて、足が大きくなることが早いと感じます。言葉が上手く伝えられない時期にきつくなったことに気づかず、そのままにしてしまうと足にも歩行にも影響が出てきてしまいますので、今回は、保護者の皆様が『適切な靴選び』と、お子様が『正しい靴の履き方を知り、動きやすい感覚を知る』こと、『靴を履く際に園で工夫していること』をお伝えいたします。
『適切な子供靴の選び方』
●まず、第一に!足のサイズを確認しましょう。
子どもの足は、個人差が大きいです。同じサイズの靴でも、肉付きのよい子、ヤセ気味の子では、きつい、ゆるいなど差があります。
「足長」「足幅」「足囲」をちゃんと測り、足のサイズにあった正しい靴を選びましょう!
最近の靴売り場では、サイズを測る計測器があり、専門の方もおられるようですので、是非ご相談ください。また、子どもの足のサイズを測るのに便利なシートやアプリも多数登場しているようです。
●もったいないから、大きめのサイズを購入する、は×。
「どうせすぐに小さくなる」「もったいない」と、大きめのサイズを選んでいませんか。 大きすぎる靴は、足に負担がかかりますし、ケガのもとにもなります。 また、いつの間にか靴が小さくなっていることに気付かずにいることがありませんか。 足の発達を妨げないためにも、3~4か月を目安に、サイズを再確認しましょう!
①【サイズ選び】
靴を履いてかかとを合わせて、指先に7~12ミリ程度ゆとりがあるのがベストです。
また、靴の中で親指が反り返ることができるくらい余裕があるものを選びましょう。
②【デザイン】
ワンタッチテープが甲についているもの、がおすすめです。
ワンタッチテープのベルトで、「足の甲」と「靴」をしっかりと固定します。
③【かかと周りが硬く、しっかりしている】
軟らかいかかとの靴では、足がぐらついて不安定になりますので、かかと部分が硬くて丈夫なものを選びましょう!
④【おこさまの運動機能の成長に合わせる】
★1歳頃の歩きはじめ~
⇒足の裏全体で体を支えることが難く、歩行が不安定ですので、素材が柔らかく足にフィットしたものを選びましょう!
★2歳頃から
⇒運動量も増えてきますので、靴のつま先とかかと持って曲げた時に、つま先から全体の3分の1の位置が軽く曲がり・フィットして、脱げにくいものを選びましょう!
⇒かかとが硬く、靴底はクッション性があり軟らかいもの
⇒靴の先が平たいもの
『正しい靴の履き方を知り、動きやすい感覚を知る』
保育所保育指針の第2章 「1歳以上3歳未満児の保育」 には「健康、安全な生活に必要な習慣に気付き、自分でしようとする気持ちが育つ」と記されています。園では、このころから、靴をひとりで履くことができるように促しています。
●左右を間違えて履いた場合
⇒園では都度「履きにくくないかな?」「くつの先がバナナになっているよ」などと繰り返し伝えています。だんだん左右の違いや履き心地が分かってくると「あってる?」などと左右が正しく履けているかを確認してくれるようになります。
●靴を履きやすくする工夫
⇒ひもやリングをかかと部分につけてあげる。
『靴を履く際に園で工夫していること』
園での工夫のうちいくつかをご紹介いたします。
① 「こどもが座って靴を履きやすいような高さ」の台(椅子)を用意する。園では高さ15センチくらいのものを用意しています。
② 「今からお靴をはこうね」など、「次に何をするのか分かるように」見通しを立てた声掛けをしていきます。
③ 上手に履けるようになるまでは、足を入れるところまで手伝い、かかとを引っ張って履く方法を伝えます。自分でやろうとする気持ちを大切にできるところまで見守りましょう!
⇒できない時は、「お手伝いしてもいいかな?」と声掛けをしてから・・
④ 履けたら「かかとをトントンね」と伝え、靴の後ろ側に足を合わせます。最後にマジックテープでしっかりと固定します。
⇒上手に履けても、履けなくても、自分で履こうとしている気持ちを認め、ほめて次につなげていきましょう!
⑤ 4・5歳児になると体幹がしっかりして、立って履ける様になりますので、しっかりと履けているかどうか、自分で確認するように声掛けをしていきましょう!
このころになると、早く履きたい気持ちが強くなりますので、つま先でトントンしたりしますが、あくまでもかかとに合わせるように伝えていきましょう!
⇒ひも靴に関しては、まだしっかりと結ぶことができず、ひもが緩んだり、取れたりするとケガにつながりますので、園ではおすすめしていません。
こどものケガにつながったり、足に負担がかかるという理由から、「保育園でお断りしている履物」もありますので、いくつかご紹介します。
・サンダル・スリッポン
・靴に穴が空いたり、擦り切れているもの
・長靴は、雨の日のみ履いてくる(小さいお子さんは長靴が好きな子が多いのですが・・)
・サイズ違い(大きいもの・小さいもの)
育児のプロによる子育てハックや、園の先生による
便利グッズをご紹介!!
- テーマから選ぶ
-
-


“好奇心・探求心”が生きる力を育む
-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて
-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』
-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン
-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと
-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段
-

【保育園園長のナルホド育児】
動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する
-

【保育園園長のナルホド育児】
「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」
-

【保育園園長のナルホド育児】
イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと
-

【保育園園長のナルホド育児】
おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む
-

【保育園園長のナルホド育児】
離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて
-

【保育園園長のナルホド育児】
子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ
-

言葉をあつかう力
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】
子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?
-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ
-

【保育園園長のナルホド育児】
子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る
-

「制限」と「出会い」
-

【保育園長のナルホド育児】
きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング
-

【保育園長のナルホド育児】
一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか
-

【保育園長のナルホド育児】
子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか
-

子どものおでかけ前の
支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】
睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】
家庭でできる遊び -

ファミリービルディング
自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の
お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】
先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方
「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】
「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する
「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】
イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン
「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】
トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】
○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン
「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加
「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」